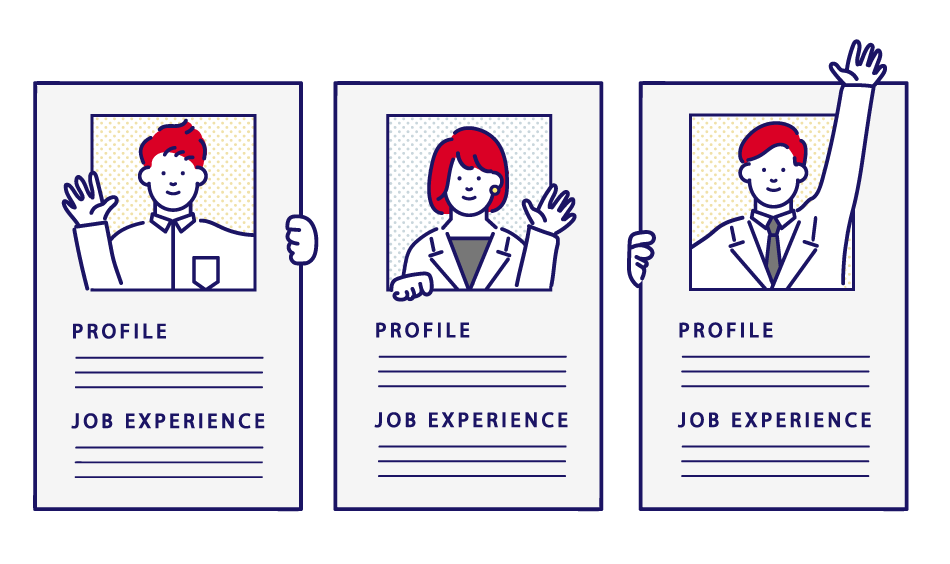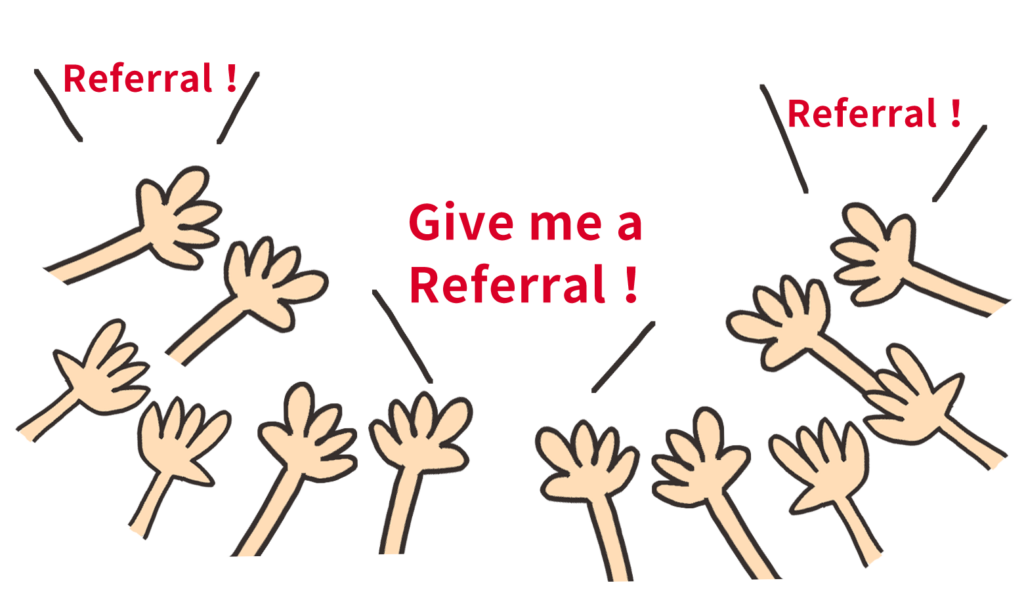Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: Apple Podcasts | RSS

【参照】英語版:Episode 841: Member Retention
このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するこんくり株式会社とビジネスの自走化を支援するActionCOACHの提供でお送りいたします。
今回は、第204回の再配信です。
第204回は「メンバーリテンション」と題してお送りいたします。英語版のエピソード841をご参照ください。
安:それでは、大野さん、大竹さん、こんにちは。
大野:こんにちは。
大竹:こんにちは。
安:今回もよろしくお願いいたします。今回はメンバーリテンションというテーマなんですけれども、大野さん、こちらについてぜひお話をいただけますでしょうか。
大野:今回、メンバーのリテンション、要するにメンバーの皆さんに残っていただく、メンバーとして継続していただくっていうことがテーマなんですけども、 なぜ今回このテーマを取り上げれたかというと、私がBNIを日本に紹介したいと思ったところにちょっと遡ることになるんですけども、 自分がメンバーとして活用していて、BNIによってだいぶ助かった部分っていうのは当時あったわけですよね。イギリスでメンバーをやってた時の話なんですけども。で、純粋に日本の経営者とかビジネスパーソンがこの仕組み、リファーラルマーケティングだったり、BNIの仕組みっていうのを使っている人がいないっていう現実を突きつけられた時に、絶対もったいないなと思ったので、 ぜひ日本にこのBNIってものを紹介する手伝いをさせてほしいっていう話をしました。
ところが、BNIを実際に日本でスタートさせて、 たくさんのメンバーの皆さんに活用してもらうことはできるようになってきているわけなんですけども、一方で、メンバー組織、会員組織なので、 いろんな理由で、辞めるっていうことを選択しないといけない人が当然いらっしゃいます。
ほとんどBNIの仕組みを理解していないであろうというタイミングでやめられてしまう方も結構いらっしゃるんですよね。1年目のメンバーの皆さんがやめられてしまう確率が高くて、そこはやっぱりすごく残念に思うんですよね。私が、これは価値があるなと思って、自分で3年ぐらいメンバーとして体験したものを日本に紹介して、今1万人を超える規模まで成長してはいるんですけども、それでもやっぱり毎年、毎月一定の割合の人はやめていってしまう。で、その中でも、もうちょっと続ければとか、もう少しトレーニング受けたらとか、もう少し使い方をこういう風にしてくれたらよかったのになっていう人もたくさんいらっしゃるわけなんですよね。
で、そういった人をどうにか減らしていくことはできないかっていうのは、私に限らず、ディレクター、 アンバサダーの皆さんもすごく日頃から腐心している部分なんですよね。ですので、今回このテーマにさせていただいてるわけなんですけど。
大竹さん、この辺について具体的なストーリーは何かありますか。
大竹:はい、ありがとうございます。私もBNIを活用しきれずに、BNIを去ってしまう方やメンバーを見ると、すごく心が痛むんですね。
そういう方を1人でも減らしていきたいと思った時に、この本質的な課題はなんなんだろうかと思った時に、 BNIの伝統として大事にされてることに、気にかけていることを知ってもらうこと、これがすごい重要なんだっていう話があったと思うんですね。
で、これはBNIに限らずなんですけれども、顧客が離れてしまう理由として、6割以上が、結局は気にかけられてないということを知った時、気づいた時にやめてしまうということが言われています。
今、BNIは、BNI ジャパンは、オンラインでミーティングをしている中で、オンラインのコミュニケーションがすごくたくさんあるんですよね。
コミュニケーションミスがより多く起こりがちな場面があるんじゃないかなという風に思っています。
あるウェブマスターの方が、この状況を変えるにはどうしたらいいんだろうかと。自分に何ができるんだろうかと考えたという話を聞きました。
彼は、ウェブマスターの役割は、1番最初にzoomを立ち上げることができること、そして、全てのメンバーを迎え入れることができるということに気づいたんですね。それで、彼はこうすることにしました。
全てのメンバーの方1人1人が入ってきた時に、お名前を呼んで、挨拶をして、一言声をかけると。これを全てのメンバーにやろうということですね。
「こんにちは、大野さん。昨日はありがとうございました」と、ちょっとしたことなんですけれども、それを続けていくことによって、このチャプターの空気、雰囲気がどんどん明るくなっていって、チャプターのサイクルを変えることができたというお話をされていました。
ちなみに、安さんは、メンバーの立場から、このメンバーのリテンションについて、何か日頃感じることってあるんですか。
安:はい、ありがとうございます。やっぱり気にかけてもらえることの大切さっていうことを先ほど大竹さんも話してくださったんですけど、 やっぱり私もメンバーの1人として、気にかけるということの配慮はとても大事だなと感じています。
例えば、ミーティングの場とか、1to1とか、そういったBNI上の仕組みはもちろん活用して、規定だったりとか、チャプターの内規だったりとか、そういったルールに照らし合わせながら活動していくということはもちろん大事ではあるんですけれど、それ以上に、じゃあ
欠席しました、書簡が出ますっていう流れの中でも、もしかしたら何か事情があるのかもしれないなとか、もしかしたら、モチベーションが少し下がってるのかもしれないなっていうことを察するとか。ちょっとした会話の中で、「どう?」って、「何か悩んでることとか、気になってることとかないですか?」っていう一言があるだけでも、実はメンバーの維持に繋がっていくことっていうのはたくさんあるんじゃないかなっていうのを私自身も経験しています。
大野さんにお伺いしたいんですが、メンバーのリテンション、つまり維持について、大切なポイントはどんなことがありますか?
大野: はい、そうですね。今回、英語版でドイツとオーストリアのナショナルディレクター、ドイツ語圏のナショナルディレクターやってくれてるマイケル・マイヤーさんの話がすごく参考になると思うんですけども、彼が言ってたのは、最初メンバーになってから3ヶ月ぐらいっていうのは、その新しいメンバーとの連絡を、チャプターでもリージョンでも、取っていくことがすごく大切で、彼の国とかリージョンでは、四半期ごとに、だから、3ヶ月に1回、ネットワーキングの夕べというか、メンバーの皆さんが、ライフパートナー、 いわゆる奥さんだったり、ご主人だったり、あるいは連れ合いっていうんですかね、そういった大切な人を呼んで、一緒にチャプターとかリージョンのイベントに参加するんだそうです。ビジネスとは直接関係ないんですけど、自分のプライベートなことを、お互いに、オープンする機会っていうことですよね。普段はビジネスの話が中心になって、あんまり家族の話をする機会ってないと思うんですけど、 自分が大切にしている家族とかパートナーを他のメンバーに紹介することがきっかけで、より関係が強くなるっていうか、深くなるっていうことは、ドイツ、オーストリアに限らず、どこでも共通することだと思うんですよね。人間関係っていうことで。
そこはすごく参考になるんじゃないかなと思いますね。
安さん、以前、ポッドキャストでファミリーデーを紹介してたと思うんですけど。
安:はい、日本語版の第165回「ファミリーデーのすすめ」ですね。
大野:はい。これも似たようなイベントの目的というか趣旨になってると思うんですけど、オーストリアとかドイツのライフパートナーっていうことに限らず、それこそお子さんを呼んだりとかして、お父さんの代わりに娘さんがウィークリープレゼンテーションをやる。「なんだ、お父さんより上手じゃないか、メンバー交代交代」って冷やかされるような場面も、私も直接目撃したことはありますけども。やっぱり、すごく、メンバー同士の関係性がすごく進化するっていうか、「進化する」ってのと「深化する」の両方だと思うんですけど、 すごくいいイベントになると思うんですよね。ビジネスパートナーとか家族の理解を得るってすごく大切だし、同じような理由で、会社のビジネスパートナーとか、 あるいは社員の理解を得るっていうことも、メンバーとしての活動を続けるっていう意味では、すごく大切な部分ですよね。
私も実際、メンバーになって1年目、最初の半年ぐらいは、なかなかリファールがもらえなかったので、「何でそんな他の会社のために大切な時間を費やしてるんだ」ってビジネスパートナーから言われたんですけど、それに対して返す言葉が見当たらなかったっていうのは覚えてますけど、こういったイベントとかを通じて関係性を深める機会を提供するのもいい方法だと思いますね。
あと、大竹さん、他にメンバーとか新メンバーと関係を築くっていう観点で大切にしてることって何かありますか。
大竹:はい、ありがとうございます。 今、大野さんの話をお聞きしていて、ちょうど私のリージョンでも、DNAチームでバーベキューをやったんですけれども、そこにファミリーデーということで家族を呼んで 日頃の感謝を伝える。私たちがこの活動ができているのは、やはり家族がいてこそ、家族の支えがあってこそだということをお伝えするようなイベントをやりました。そうすることによって、接点を増やす。接点を広げることによって、より強固な関係を築いていくことができるんだなっていう風に感じています。
で、今のご質問の話なんですけれども、メンバーと関係を築くために、3つのポイントが英語のポストキャストでは紹介をされていますので、それを参照しながらお話をしたいんですけれども、 1つ目は、共通点を見つける。共通点を見つけることができれば、会話の出発点ができるということですね。2つ目は、自分から何かを分かち合う必要があるということですね。人はどこまでこの人に話をしていいんだろうかと、相手を見ながら探っていくところがあると思うんですよね。なるべく自分から先にオープンになるということがすごく重要なんじゃないかという風に感じています。そして3つ目は、感謝と承認を具体的にするということですね。誰かにお礼を言うときは具体的にするということが大事なんだという風に言われています。例えば「この2か月の間にリファーラルを3件も紹介してくれて本当にありがとう」と。「3人のご紹介者のうち、私は100パーセント全て成約することができました」と。そして、さらに、「彼らはすでに2度目、3度目の注文してくれていて、3人もその先の新しいお客さんを紹介してくれたんだ」そういう風に具体的に感謝、お礼を伝えるということが関係を築く上で重要だという風に言われています。
安:ありがとうございます。なるほど。やはり感謝の気持ちが最後に出てきましたけれども、 その感謝の心をしっかりとメンバーにも伝えていくということが、もしかしたらメンバーリテンションの本当に大事なワンエッセンスなのかなと私も感じました。ありがとうございます。
それでは、そろそろ終わりに近づいてまいりましたけれども、大野さんからメンバーの皆さんへメッセージはありますか。
大野:はい。いろんな理由で退会を選択しなくちゃいけないっていうメンバーの方はいらっしゃるんですけども、 割と、本当の理由って皆さんなかなか言ってくださらないと思うんですよね。でも、本当に1番多いのは、おそらくこの人間関係で、 やっぱりチャプター内でのメンバー同士の関係性がすごく大事だと思うんですね。
お互いがすごくケアしてるよっていうことを、言葉だけじゃなくて、行動でも示すっていうことがすごく大切かなという風に思いますね。
安:ありがとうございます。大野さん、大竹さん、今回も素晴らしいお話ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたか。皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。
よろしければinstagramやYouTubeで発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が、次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。
一緒にこのポッドキャストを成長させていけたらと思っています。それでは、次回もオフィシャルBNIポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!