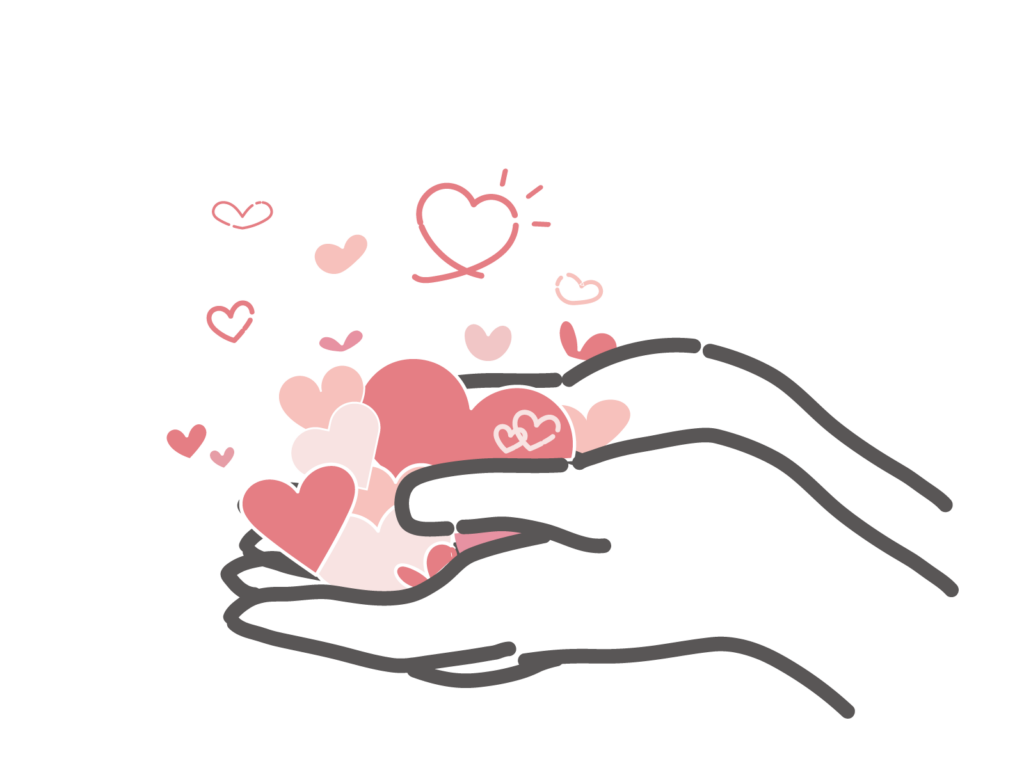Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: Apple Podcasts | RSS

このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するこんくり株式会社とビジネスの自走化を支援するActionCOACHの提供でお送りいたします。
今回は、第220回の再配信です。
第220回は「行く価値あるの?」と題してお送りいたします。
安:さあ、大野さん、今日は「行く価値あるの?」という、またキャッチーなテーマなんですけども、今回はどんなお話になるんでしょうか?
大野:今回は沖縄ですけども、毎年ナショナルカンファレンスが開催されるので、「それって行く価値あるのか?」っていうお声をよくいただくので、その辺をちょっと掘り下げていきたいと思っています。
安:今回のテーマで「行く価値あるの?」っていう言葉は、実は私があるメンバーに今回のナショナルカンファレンスのお誘いをしてみた時の反応なんです。今回、沖縄なので「沖縄に行くの?」って聞いたら、「え、それって行く価値あるんですかね?」って聞かれちゃったんですよ。これって結構私の中では衝撃だったというか、まあ、そうやって実際に言う方もいらっしゃるは、いらっしゃると思うんですが、でもそういうイベントって、自分から価値を創りに行く良いきっかけになるんじゃないのかなって私は思ったので、ちょっとこの辺を掘り下げてみたいなって思っています。
大野:はい、ありがとうございます。多分、ごく自然なレスポンスなんだと思うんですよね。平均的なレスポンスだと思います。安さんが今おっしゃったような提供されるものを受け取りに行くとか、あるいは自分でそれに価値を見出しに行くっていう意識っていうのは、多分かなりレベルの高い話で、なかなかそこまで普通の人は発想がいかないと思うんですよね。なのでどういう価値があるのかっていうのは、今回皆さんにできるだけお伝えできればいいかなと思います。ナショナルカンファレンスというのは、イベントに参加するっていうこと以外でも、いわゆる一般的にネットワーキング、人と会うっていうことを、そういった機会を活用するということを考えた時に、予定して計画的に誰かと会うっていうことはするじゃないですか、みなさん。アポを取って、例えば大竹さんとミーティングをするとか、ランチを食べるとか、安さんとコーヒー飲むとかっていうのは、アポを入れてみなさん自然にやってるんですけど、これって予定されていた想定内の出会いっていうんですか、既知の人、お互いに知ってる人同士が会うっていうことなんですけど、これはここで何か新しい化学反応が起きるとかっていうことは予想してないわけですよね。計画されてなかった出会いっていうのは、そこからのリターンっていうのが予測できないわけですよ。なので、その価値の大きさっていうのは、予定していた出会いよりも予定してなかった出会いの方が、大きくなる可能性っていうのは高いんですよね。無限大にある。それは人脈論的によく言われることなんですけど。なので計画的にいろんな人と、例えばBNIの方皆さんであれば、1to1を予定していくとか、あるいはチャプターミーティングで定期的にビジターの方との出会いはもちろんあるんですけど、もちろんそのビジターさんとの出会いっていうのは新しい出会いなので、予想していなかった化学反応が起こる可能性はやっぱりあるんですけど、そこに皆さんが例えばナショナルカンファレンスに参加するっていうことを考えた時に、どんな出会いが待っているか分からないっていう無限の可能性がそこに秘められているっていうのは、これって皆さんお一人お一人が覚えておかなくちゃいけないっていう貴重な事実としてあるんですよね。大竹さん、カンファレンスに参加する意義みたいなところでお伝えしておきたいことってありますか?
大竹:はい、そうですね。今、大野さんのお話を聞いていて私が思い出したのは、「パルプンテ」っていう呪文なんですけど、私の世代で皆さん知ってる方いらっしゃると思うんですけど、要は何が起こるか分からない呪文なんですよね。すごくいいことが起こることもあれば、ちょっとだけいいことが起こることもあれば、何も起こらないこともあって、ちょっと悪いことが起こることもあるっていう、そういった呪文なんですが、結構コストがかかるんですよ。MPが消費されるんですけどね。ただ、唱えないと何も起こらないっていうことがあると思っていて、どうしてもやっぱりコスパとか、タイパとか考えてしまうと思うんですよね。でもこれ、もしかしたら人生を楽しむ秘訣みたいにもなるのかもしれないけど、予定していないこととか、想定していないことを起こそうと思ったら、自分から行動を起こしていかないと変わっていかないのかなという風に思うんですよね。でも、時間とかお金とかリソースは限られているわけで、どうやってそれを選択していくのかといったときに、想定外のことが起こる可能性を高めるにはどうしたらいいのかなという風に思ったときに、私はこの今回カンファレンスで一つの出会いの場だと思うんですけど、人と人との出会いっていうのは、すごく化学反応が起きやすい場だと思うんですよね。かつ、なぜBNIのこういったカンファレンス、イベントに参加する価値がより高いのかなというふうに思ったときに、皆さんギバーズゲインの姿勢を持っているからこそ、より多くの出会いの価値、より多くの化学反応が生まれる価値があるのかなというふうに思うんですよね。もしそこに集まる人たちが自分のことしか考えてなくて、「なんか、売れないかな」みたいな奪うことばかり考えていたとしたら、そこから化学反応が生まれる可能性って限りなく低くなっちゃうんじゃないかなと思うんですね。もちろん0じゃないとは思いますけれども。ただ、そういったギバーズゲインの姿勢を持った人がそれだけ集まるってすごい奇跡だと僕は思っていて、そういう場が私たちに用意されている。これってすごいことなんじゃないかなというふうに私は感じています。
大野:はい、ありがとうございます。本当そうですよね。今もうこの収録の時点で1500人以上の人が登録されているっていうことなんですけども、目標は多分確か2500 ぐらいの参加者ということで、それだけギバーズゲインを実践、日頃からされている、意識している人たちが集まっているということの価値ですよね。イベントの価値っていうことだと思うんですね。はい、ありがとうございます。ところで、先日ですね、BNI AI ディレクターコンサルタントっていうのをですね、チャットGPTに実装しまして、ディレクターの皆さんに公開しました。そこで早速なんですけれども、「ナショナルカンファレンスって行く価値あるのか?」っていう質問をしてみました。ちょっと聞いてみましょうか。チャットGPTからの回答に入る前に、私個人的に思うんですけど、これ前からよくお伝えしてはいるんですけど、多分初めて聞かれる方もいるので、BNIのメンバーとしてプログラム利用料を払って投資してメンバーとして活動されてるんですけど、でもやっぱりせっかくメンバーなのにこのナショナルカンファレンスに参加しないっていうのは、その価値、自分が投資してる価値の半分以上を捨ててしまっているような、僕は感覚があるわけですよ。でもそれはディレクターの目線ということなので、なかなかやっぱりチャプターのメンバーの皆さんって、そういったことを感じるっていうことがなかなか難しいと思うんですよね、普段。なのでこのチャットGPTでいろいろと素晴らしい価値のポイントを教えてくれているので、シェアしていきたいなと思ってます。全国のBNIメンバーとのつながりが作れる、ということは、より多くのリファーラルの機会だとか、さっき言った化学反応を起こしやすいっていうことですよね。その結果として、そこで得られた人脈だとか情報っていうのは、チャプター全体の成長にもつながりますよねっていうのが1つ目ですね。2つ目がビジネス拡大のチャンス。これはやはり日本全国、それから世界中からいろんな人が参加してくれますので、その成功事例を知るということで、新しいビジネスの視点を得ることができたりとか、そして大きな人数、大きなネットワーキングの機会なので、新しいマーケット市場とか、あるいはその提携先なんかを見つける機会にもなりますよね。そして3つ目が学びの機会です。これはもちろん大きな学びの機会ですけども、やっぱり世界各国から、あるいは国内選りすぐりのスピーカーをお招きしていますので、トップクラスの講演だったり、トレーニングというのが用意されていますから、ビジネススキルとか、BNIのよりうまく活用していく方法なんかを学ぶことができます。BNIの成功メソッドみたいなのを直接学んで、チャプターに持ち帰ることができるというのが3つ目の価値ですね。4つ目が楽しく魅力的なイベントであるということ。全国のメンバーと交流する機会でもあるし、楽しく学べる特別な機会であるっていうことですよね。特にチャプターで一緒に行ったりすると余計に楽しくなりますからね。なのでそういった誘い合っていくっていうことで楽しみの要素が増えるし、カンファレンスで経験できることって、ビジネスだけじゃなくて人生にとっても貴重な財産になるというようなコメントを出してくれていてます。5つ目のおすすめとしては、やっぱりAIもチャプター単位での参加を勧めてくれてますね。これは本当にそうだと思います。チャプター全員が参加できるのが理想的だと思います。実際、過去に東京から京都に全員で参加するとか、新宿から全員で参加するっていうチャプターありましたけど、中には現地で京都で部屋を借りて、チャプターミーティングそっちでやろうっていうことをやってたチャプターもありました。いいアイデアですよね。チャプターの定例会やるとか、チャプターのイベントもカンファレンスと同時に向こうで企画してみるっていうのもいいアイデアだなと思いますよね。みんなで学ぶ、あるいはチャプターでまとまってグループで参加すると、持ち帰った学びっていうのも、チャプターチーム全体の成長につなげられるし、みんなで参加するとより多くの情報をシェアできますよね。皆さん視点が違うので、それを振り返って学びのポイントをシェアするってのはやっぱり価値が高くなりますよね。6つ目は、実はチームビルディングの観点なんですけど、これすごくやっぱり大きいなと思いました。共通の体験をできるじゃないですか。普段のチャプターのミーティングとか、チャプターのイベントと違って、非日常の体験をみんなでするわけなんですよね。なので一緒に学び、感動を共有するっていうことができるので、メンバー同士の絆が深まるっていう効果がありますよね。終わった後、例えば帰りの移動中だったり、あるいは今回沖縄なので、沖縄に少し一緒に残って一緒に振り返りをして、学んだことをシェアしたりするということで、チームの一体感が高まるし、チャプターのビジョンをより明確にする機会にもなるんじゃないかって言ってくれてますね。私達のチャプターもこんな風にできるとかね。あるいは、そういった新しいビジョンに磨きをかけるとか、目標を持つきっかけになるという点ですね。成功しているチャプターの事例を知ったりとか、チャプター全体で取り入れるべきポイントっていうのを話し合うことができるので、またとない機会になるんじゃないですかね。
安:ちょうど何となくチャプターの中だけでビジネスをしようとしていたところが、カンファレンスとか、あるいはグローバルコンベンションといったイベントに参加をしたことによって、視野が広がって、ビジネスのレベルがグローバル化したっていう事例も実際にあるんです。今の私も共感できるところが多いなと思いました。
大竹:今のお話の事例なんですけど、静岡の法貴さんだったと思うんですけど、あるカンファレンスに参加した時に海外のゲストが来ていて困っていらっしゃったんですよね。「手助けできることありますか」っていうことで、ちょっと手助けをしてあげたそうなんですね。そしたら「どんなビジネスしてるの?」って話になって、実は法貴さん、今その方のビジネスの日本の展開を任されているというか、手伝っているということなんですよね。やっぱりギバーズゲイン姿勢でお互いに関わることによって、大きなチャンス、多分それ予定してなかったと思うんですよ、本当に。そういうことが起こるんだなということを聞いたことがありました。
大野:はい、ありがとうございます。あと、例えばリーダーシップチームの方とか、役職持たれてる方なんかは視野が広がるじゃないですか。例えば4月なので、着任してすぐのイベントですから、どんなチャプターにしていきたいか、そういった考えを新たな視点で思いを巡らすっていう機会をチームでできる。あと、ほかのチャプターのリーダーの皆さんとか、ディレクターとの交流の機会もあるので、日本ももちろんですけど、海外のすごい成功しているリージョンとか国とかってありますから、やっぱりリーダーシップとしての視野もけっこう広がると思うんですよね。もう一つ、最後ですね。チャプターの士気向上っていうところにつながるって言ってくれてるんですけども、やっぱりせっかく参加したんだから、学んだことを生かしてもっと良くしていこうとか、成長させようという前向きなプラスのエネルギーが溢れてますね。参加することができたメンバーが参加できなかったメンバーに学びをシェアするということで、チャプター全体の成長にもつながるというふうに言ってくれています。
安:いや、AIってすごいですね。こんなに具体的にアドバイスをくれるんだなと思って、今非常に興味深く聞いてたんですけど。それではそろそろ終わりに近づいてまいりましたが、大野さんや大竹さんからメッセージはありますでしょうか。じゃあ、まず大竹さんからお願いします。
大竹:はい、ありがとうございます。チームで参加することの価値について、私も去年のハワイのカンファレンスで感じたことだったんですけど、チームで参加をして、最後の日に振り返りのミーティングをしたんですよね。それぞれ共通のセッションに参加していることもあれば、別々のセッションに参加していることもあって、共通のセッションに参加してても全く見方が違うんですよね。あ、そういう見方があったんだ、そういう意味だったんだっていうことで、本当に理解が深まったんですよね。その時間を共有することによって、お互いの信頼関係がすごく高まったっていうことがあるので、本当にチームで参加することの価値というのは私自身も感じました。
安:ありがとうございます。
大野:いや、これ振り返り大事ですよね。やっぱりやるのとやらないでは全然結果が違うと思うので。私からは参加する前にチームとして目標を設定する、参加する際の目標、チームとしての目標を設定するということをぜひおすすめしたいんですよね。このカンファレンスでこれこれを学ぼうとか、チャプターに持ち帰ろうといったテーマを決めておくと、より意識的に学べると思うので、ぜひやってみてください。
安:はい、ありがとうございます。やっぱり私もメンバーとして何回もナショナルカンファレンス出てますが、みんなで行くっていうことをすごく価値があるなと感じています。今、大野さんがお話してくださった目標設定、そして大竹さんがおっしゃったいろんなところにみんなで行ってみる、それによる気づきを得る、そしてまたそれを振り返り、シェアするっていうことの大事さをすごくあらためて私も学ばせていただきました。なので、沖縄でもしっかり目標を持って、そしてちゃんと振り返りしていきたいと思います。ぜひメンバーの皆さんにも同じように目標と振り返りをやっていただきたいなと思いました。ありがとうございました。
大野:ありがとうございました。
大竹:ありがとうございました。
安:最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか。
大野:まだまだ!
大竹:ちょっとまった!
安:何ごとですか。
大野:大事なお知らせを忘れています。
安:大事なお知らせ。もしかして。
大野:そう、あれあれ、それそれ。
安:これか。実はナショナルカンファレンスでこのオフィシャルBNIポッドキャストの公開収録をやることになったんですよね。すごい楽しみなんですが。
大野:楽しみそうに聞こえないよ。
安:本当に楽しみにしてますって。いや、これ割と初の試みなので、ナショナルカンファレンスの中では。はい、楽しみにしてますよ。
大野:トピックを今募集してるんですよね。
安:はい。実は2月16日とあともう少しで締め切りが来るので、ぜひ多くのみなさんからトピック募集したいなと思っています。専用のリンクがありますので、是非是非そこから応募していただけたら、もしかすると当日のカンファレンスの公開収録の時にお話を直接お聞きするかもしれないので、是非皆さんからの応募お待ちしております。
大野:リスナーの皆さんで一緒に沖縄に行っていただくと、きっと楽しいんじゃないかなと思ってます。お願いします。
安:お願いします。ということで、最後までお聞きいただきありがとうございます。皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければInstagramやYouTubeで発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。それでは次回もオフィシャルBNIポッドキャストでお会いしましょう。See you next week.