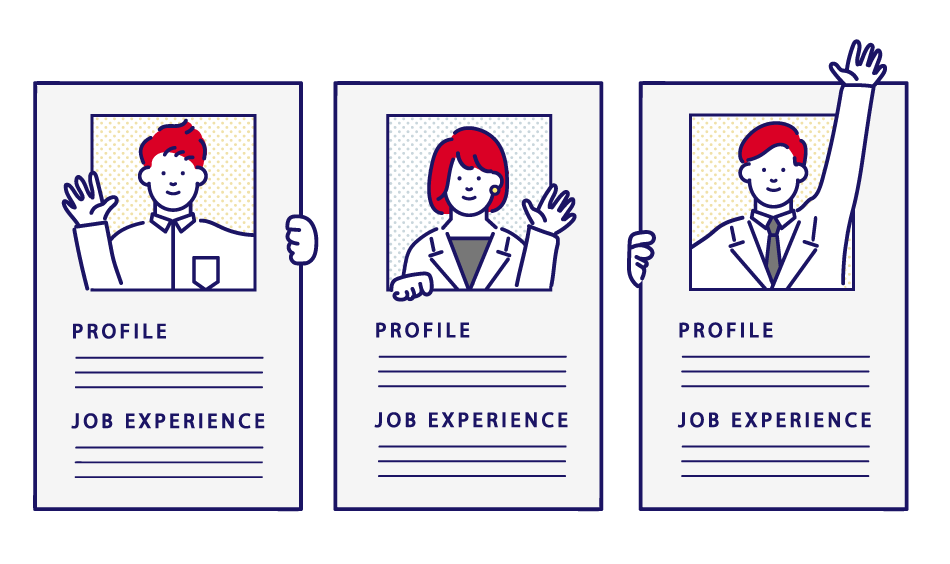Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: Apple Podcasts | RSS

【参照】英語版
Episode 922: The Power Beneath the Surface
このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するこんくり株式会社とビジネスの自走化を支援するActionCOACHの提供でお送りいたします。
第255回は「リファーラル要りません」と題してお送りいたします。
英語版のエピソード922をご参照ください。
安:大野さん、大竹さん、本日もよろしくお願いいたします。
大野:よろしくお願いします。
大竹:お願いします。
安:大野さんの今日お召しになっているお洋服がBNIとアイスホッケーでしょうかね。
素敵なデザインなんですけど。
大野:ちょっと見ていただこうかな。
これTシャツなんですけども、今まだ名古屋にいるんですけど、昨日の夜アイスホッケーの試合がありまして、BNIが応援している名古屋オルクスっていうプロのアイスホッケーチームの試合で、BNIが冠スポンサーとなってやってたんですね。
相手は東京ワイルズというチームだったんですけど、ものすごくいい試合で、最初4対1で勝ってたんですよ。
4対1で勝ってたんですけど、最後の最後に追いつかれてしまって、サドンデスの延長を5分間やったんですけど、そこで先に1点入れられてしまって、結果5対4で負けてしまったんですが、すごい盛り上がりました。
結果負けてしまったんですけどね。
結構BNIの特に名古屋あたりの方たちがたくさん来てくださって、30人35人くらい来たのかな。
お子さん連れてくださった方もいらっしゃって、初めてアイスホッケーを観戦するという方もいらっしゃったんですけど、みんなで防寒着の上にこのTシャツを着て応援してました。
安:そうだったんですね。
これは試合をしているプレイヤーの方々もきっとすごくその応援に励まされたんじゃないかなと思います。
それでは今回のテーマが「リファーラル要りません」ということなんですが、大野さん、こちらについてお話をしていただけますでしょうか。
大野:はい。
これはウィークリープレゼンの時に、特に男性が多いように私は思うんですけど、「実は僕そんなにリファーラル皆さんからいただきたいと思ってないんです」みたいな発言をされる方が時々いらっしゃるんですよね。
おそらくこれをお聞きの皆さんも「うちのチャプターにもいる」と思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、どうしてそういう発言になるのかというところとか、一緒に探っていければと思ってます。
実際最近あるチャプターのメインプレゼンテーションでメンバーの方がおっしゃってたんですけども、半ば過ぎたぐらいのところで先ほどの「実は私は皆さんからリファーラルいただきたいと思ってないんですよ」みたいな話をされてたんです。
やっぱりそういう方結構いらっしゃるんだなと思ったんですけど、多分そもそもなんですけど、BNIのチャプターが存在している意味とか意義みたいなところをちょっと偏った見方をしてしまっているんじゃないかなという風に思うんですよね。
間違っているとまでは言わないんですけど、例えばチャプターのウィークリープレゼンテーションの目的が、自分がリファーラルをもらうことが100%その目的であるみたいな風に思ってしまうと、「いや実は私もらいたいと思ってないんです」という発言につながるのはある意味自然なことかもしれないと思うんですよね。
でもそうすると聞いてる方がしらけちゃうじゃないですか。
この人のためにと思って聞いて、しっかりとプレゼンテーションを聞いて、日々の生活の中でミーティングとミーティングの間の9990分の中でリファーラルを見つけられたらいいなと思って聞いているのに、なえちゃいますよね。
それはもったいないというか、もらえなくなっちゃうからもったいないという意味ではなくて、チャプターの価値っていうんですかね、あるいはみんなでビジネスチームとして時間を投資してメインプレゼンだったらメインプレゼンテーションの時間を持っているのに、それがリファーラルをもらうの必要ないということは、欲しくないのねと。
必要ないのねと言うと、メインプレゼンテーションの時間自体が台無しになってしまうというか、価値を下げてしまうと思うんですよ。
じゃあどういう風に考えたらいいかということなんですけど、チャプターの存在する先ほどの意義というところで言うと、チャプターって例えば50人いれば50の専門家が揃っているわけですよね。
いろんな分野の専門家がいて価値を持ち寄っている。
その持ち寄っている価値を生かしてチャプターの周りの人たちを、みんなが普段生活しながら、あるいは仕事しながら接点を持つ人たちの困りごとを解決したり、あるいは何か力になっていくというところ。
そういう機会を探っていくということを考えると、ウィークリープレゼンテーションの目的は、メインプレゼンテーションを担当されたメンバーの方が、どのようにしてどんな人たちにどんな価値を届けているのか、提供しているのか、あるいはどんなふうに役立つことができるのかというのをプレゼンするという目的になるわけですよ。
それを聞く他のメンバーたち、「あ、なるほど。
誰々さんはそんな風にこういう人たちを普段助けてるんだな」というのが理解できるわけですよね。
理解できると、同じような人たちと自分が会った時に誰々さんを紹介しようということにつながるわけじゃないですか。
なので自分たちがリファーラルをもらうために普段活動してるとか、ウィークリープレゼンテーションはリファーラル欲しい人がやるもんだみたいな風に思ってしまうと、すごく偏ってしまう。
間違ってるわけではないんですけど、むしろチャプターの皆さんがチームとしての力をつけて価値を高めていく。
それを使ってどんどん周りたちのお役に立っていくんだという、ある意味ギブのサイドから自分たちのチャプターだとか、ウィークリープレゼンテーションの時間だとか、あるいはチャプターミーティングというものを捉えると、もっとチャプターの存在意義を高めることになるし、自分たちの価値を使ってどんどん多くの人たちの役に立っていくことができるという風に捉えると、全く変わってくると思うんですよ。
先ほど申し上げたメインプレゼンテーションのメンバーの方も、そんなこと言わなくていいわけですよね。
自分は欲しくないなんて言う必要は一切なくて。
でも人を助けたくないとか、人の役に立ちたくないっていうんだったら元も子もなくなってしまうんですけど、でもおそらくBNIだったらコアバリューの一つの理念のギバーズゲインというものに、少なくとも共感して参加されている方がほとんどでしょうから、それを体現していく。
それがチャプターの最大の存在目的であるというふうに捉えれば、そんな言葉は出てこないと思うんですよ。
だからどんどんみんなで一緒に協力し合って、みんなが持っている価値をどんどん届けていこうということで考えれば、非常にシンプルだしパワフルだと思うんですよね。
大竹:大野さん、ありがとうございます。
すごい本質的な話だなと思いながら聞いていたんですけど、私今の話を聞いていて、今田舎に住んでいるんですけど、近所の方のことを思い出しました。
私の地域はほとんどが70代80代の方で、元からその地域に100年200年と住んでいて、立派な家があって畑があって、今皆さんは年金をもらっていて、いわゆる悠々自適だと思うんですよね。
特に畑を耕したりとか働かなくてもいいような状態だと思うんですけど、ただ皆さんやっぱり畑を耕し続けているし、動き続けていらっしゃるんですよね。
でもそれは別に自分が食べていくためとかそういう事ではなくて、与えるためなんですよね。
近所の人に野菜とかできたものを、おすそ分けしたりとか、子どもとか孫とか親戚におすそ分けしたりとか、与えるために動かれてる、働かれてるというところなんですね。
今の話でいうと、「リファーラル要りません」というのは、「今は売上が順調だからリファーラル要りません」というところでいうと、「今お腹いっぱいだから畑を耕しません」と言ってるのと同じなのかもしれないなというふうに感じました。
今お話があったようにウィークリープレゼンテーションなりメインプレゼンテーションの時間をもらうことにフォーカスを当てているとそういう話になってしまうのかなと。
そうではなくて与えるための時間、自分が持っている価値をギブするための時間、それをどうやってギブするかというところ。
そこに焦点を当てた時間にしていくとまた見方が変わってくるのかなというふうに思いました。
もう一つは、今だけにフォーカスをすると「今はリファーラル要りません」ということだと思うんですけど、リファーラルを通じて信頼関係を作っていく、関係構築をしていくこと。
その信頼関係というのは資産だと思うんですね。
今役に立たなかったとしても、未来自分の事業が永続的に順調なわけが多分ないと思うんですよね。
将来何か大きな変化があったりとか事業が不安定になった時に、関係資産というのはすごく力を発揮してくれるんじゃないかなというふうに思います。
大野:そうですよね。
そもそもその事業をやっていることの意義というか意味、目的みたいなところで、おそらくその価値をいろんな多くの人たちに届けようということがあるんでしょうから、それ自体を否定することになっちゃうと思うんですよね。
「リファーラル要らないんですよ」と言って、それではなんでその仕事してるんですかという話になってしまうので、自分がお客さんを紹介してほしいということではなくて、自分はこういうふうにいろんな人たちに価値を提供することができる、こういう人たちにこういう価値を提供することができるんですということをしっかりと伝えていくことで、その価値をチャプターのメンバーたちの力を借りてどんどんさらに多くの人たちに届けられる、多くの人たちの役に立てるというところで捉えると、さらにプレゼンテーションの価値も高まるし、チャプターの価値もメンバーの価値も高まっていくことにつながると思うんですよね。
大竹:そうですね。
単にリファーラルを提供するということではなくて、BNIの活動を通じて今はどんなことを与える機会なんだろうかと。
与える機会としてすべての活動を見ていくと、見方がちょっと広がっていくんじゃないかなというふうに思いました。
大野:そうですね。
そういう与えるってところにフォーカスをすればギバーズゲインの言葉の通りで帰ってくるということですもんね。
安:それではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、大野さんや大竹さんからメンバーの皆さんへメッセージはありますか?
大野:はい。
今回はそのままなんですけども、多分皆さんのチャプターにもそういう方見たことあるとか聞いたことあるって方も結構今回いらっしゃると思うので、チャプターでその人に直接「これ聞いといた方がいいよ」というとちょっとトゲがあるかもしれないので、チャプターのエデュケーションでこういったものをご紹介いただけたらいいんじゃないかなという風に思います。
大竹:ありがとうございました。
「順調だからリファーラル要らない」というのは今の視点なのかなと。
BNIの価値は未来の選択肢を増やすことにあるのかもしれないと思いました。
今必要な紹介だけにフォーカスするのではなくて、未来自分を助けてくれるかもしれない人間関係を育てる場所として考えていただけると、より視野が広がるのかなと思いました。
安:大野さん、大竹さん、ありがとうございます。
まさにプレゼンテーションの場で「こういう人を紹介してください」ではなく、「自分の仕事がこんな人のお役に立てるんだ」というふうに表現されていくと、結構多くの方にそのお話や価値が届くんじゃないかなと私としてもすごく感じました。
ありがとうございました。
大野:ありがとうございました。
大竹:ありがとうございました。
安:最後までお聞きいただきありがとうございます。
今回のお話はいかがでしたでしょうか?皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。
よろしければInstagramやYouTubeで発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。
皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。
一緒にこのポッドキャストを成長させていければと思っています。
それでは次回もオフィシャルBNIポッドキャストでお会いしましょう。
See you next week.